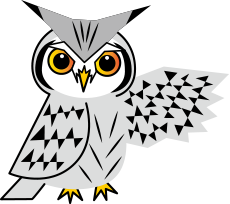解体工事の流れをわかりやすく解説 トラブルとストレスを減らそう!
解体工事が必要になったけど、何から始めていいかわからない…。初めてのことは誰にでも不安です。ましてや解体工事の段取りなんて複雑そうで益々よくわからないという方もたくさんいることでしょう。
しかし、解体工事の大まかな流れを知っておくことで、余計なトラブルを未然に防ぎ、ストレスを減らすことに繋がります。この文章に軽く目を通して、心の準備を整えてみてください。
まず、解体工事を実際に始める前にすべきことをご紹介します。
解体工事をすると決めれば、まずはどこの業者に依頼するのか決める必要があります。インターネットで調べると、大手業者の見積もり等をまとめて比較している記事もあり、参考になります。
安さと作業工程の速さを売りにしている業者もよく見かけますが、解体工事は安全が最優先事項なので最も信頼できる業者に依頼しましょう。
選ぶポイントは、合法的に解体工事を施工できる業者か、工事保険に加入しているか、単なる受注のみを行う会社ではなく自社施工を行う業者なのか、という点です。
合法的な業者は、解体作業をするのに必要な、建築業許可証や解体工事業登録を取得しています。また、解体作業後にでるゴミ(産業廃棄物等)を然るべき手段で処理し、マニフェストと呼ばれるそれらの廃棄物を処理した過程の記録を発行してくれます。
実際に電話で話すよりも直接会い、合うか合わないか決めるのも良いでしょう。連絡がつきにくい業者も、後々トラブルの原因になることがあるので、物理的にも心理的にも話しやすさを重視することは理にかなっています。
前段と関係しますが、見積もり時にも注意すべき点があります。
見積もり内容が簡素すぎたり複雑すぎたりする業者は要注意です。業者の慣習なのか、取引相手との信頼関係を大事にしており見積もり内容を詳しく書かない業者も多いようです。
「解体工事 一式〜円」というように明細のない見積もり書や、素人にわかりにくい表現で埋まっているような見積もり書を受け取り不安を感じたらすぐに担当者に相談をしましよう。
信頼できる業者が見つかり、契約内容に納得できたら請負契約を結びます。契約書で見るべき点は5つです。
解体工事と言っても、全て取り壊すのか、一部を残すのか、一部のみ解体するのか、と詳しく特定されます。
事前に相談した内容と合致しているのかよく確認しましょう。相互のやり取りをより確実にする方法として、図面に作業範囲を明記したものを用意することも良いです。
まずは、見積もり時に提示された金額と相違が無いか、無断の書き換えが行われていないかを確認します。
さらに、工事代金の支払い時期が、解体工事から何日以内までなのか確認することも重要です。その際、一括払いなのか分割なのか、カード支払いが可能なのかも併せて見てみましょう。加えて、解体工事の支払いにローンや助成金を使用する場合は、その旨を事前に伝えておくとスムーズです。
工期の目安が明記されていないと、工期が大幅に遅れているときに責任を問うことができなってしまいます。また、災害などやむを得ない事情で工期が遅れる際のどのように対処されるのか(例えば、遅延が判明したらすぐに施主に連絡をするなど)も決めておくと安心です。
反対に、人員や機材不足などの業者側の理由で遅れる場合、無断で追加費用を支払わなくて済むように事前に決めることもトラブルを避ける為に良いでしょう。
法律用語だからと言って読み飛ばしてはいけません!
瑕疵担保責任は、もし解体後の状態に欠陥や不具合がみられ解体作業として不十分である(瑕疵がある)場合、業者側が負う責任の事です。瑕疵担保責任が明記されている事で、不具合があっても、一定期間に渡って業者側が責任を負い、施主は余計なコストの支払いを免れることができます。
また、損害賠償が発生するのは、作業中に一般人を怪我させてしまったり、他の建造物に傷をつけてしまった場合です。原則、業者側が責任を負いますが、より責任の所在を確実にする為に明記して負いた方が良いでしょう。
解体工事が終了時期は、必ずしも引き渡しの時期と同じではありません。一般的には、施主の立会いのもと作業の終了を確認してもらい、終了となります。
引き渡しの時期を明記することで、工事の遅れの判断基準にもなりますし、直接現場に立ち会えない場合のスムーズな引き渡しにつながります。
解体工事中に騒音や埃等が発生する場合は特に、近隣住民の方にご迷惑をおかけするので事前に説明し、理解を得てもらいましょう。
業者の方が挨拶してくれることもありますが、施主も同行することでより良いコミュニケーションを取れるので、労力を惜しまずに挨拶に行き、円満なご近所づきあいを継続してください。
工事の大まかな流れを以下のようになります。
外構の解体:重機の搬入や足場、養生の設置のためにスペースを確保します。
↓
足場、養生の設置:養生を設置することは、粉塵や木材の飛散防止、騒音の軽減に必要です。
↓
屋根、内装の解体:建設リサイクル法を遵守する為に、素材ごとに手作業で分別しながら解体していきます。
↓
建物本体の解体:壁や柱などの建物の主要部を解体するので、主に重機を使用します。粉塵の飛散を防止するために散水しながら行います。
↓
建物基礎、地中物の撤去:地中にある建物の基礎や配管などを解体、撤去します。ここで初めて明らかになる地中物もあるので、撤去のため追加費用が必要な場合もあります。
↓
整地:解体工事で掘り起こされた土地を平らにします。施主が立ち会って確認できます。
解体工事が完了してもすべてが終わるわけではありません。
解体作業自体が終了したら、施主は現場に立会い最終確認をします。一般的に、ここで引き渡しとなり、正式に解体工事が終了します。
建物が取り壊されれば、登記簿にある家屋が無くなったことを登記するために、法務局に申請しなければなりません。
不動産登記法57条で、解体工事後1ヶ月以内に、その旨の滅失登記をすることが義務付けられているので必ず忘れずに行ってください。登記していなければ、その土地を売却することができなくなるばかりではなく、固定資産税として課税されてしまいますので、ご注意ください。
解体工事の流れへの理解は深まりましたか?解体工事を依頼する時と、工事後の登記手続きが少々面倒ではありますが、全て必要なことなので都度確認しながら進めてみてください。
解体業者を選ぶことにストレスを感じるならば、少しお金はかかりますが中間業者に頼んで斡旋してもらう方法もあります。少しでもストレスとトラブルが少ない解体工事への手助けができていれば幸いです。
しかし、解体工事の大まかな流れを知っておくことで、余計なトラブルを未然に防ぎ、ストレスを減らすことに繋がります。この文章に軽く目を通して、心の準備を整えてみてください。
解体工事前にやること
まず、解体工事を実際に始める前にすべきことをご紹介します。
依頼する業者を選ぶポイント
解体工事をすると決めれば、まずはどこの業者に依頼するのか決める必要があります。インターネットで調べると、大手業者の見積もり等をまとめて比較している記事もあり、参考になります。
安さと作業工程の速さを売りにしている業者もよく見かけますが、解体工事は安全が最優先事項なので最も信頼できる業者に依頼しましょう。
選ぶポイントは、合法的に解体工事を施工できる業者か、工事保険に加入しているか、単なる受注のみを行う会社ではなく自社施工を行う業者なのか、という点です。
合法的な業者は、解体作業をするのに必要な、建築業許可証や解体工事業登録を取得しています。また、解体作業後にでるゴミ(産業廃棄物等)を然るべき手段で処理し、マニフェストと呼ばれるそれらの廃棄物を処理した過程の記録を発行してくれます。
実際に電話で話すよりも直接会い、合うか合わないか決めるのも良いでしょう。連絡がつきにくい業者も、後々トラブルの原因になることがあるので、物理的にも心理的にも話しやすさを重視することは理にかなっています。
見積もり時の注意事項
前段と関係しますが、見積もり時にも注意すべき点があります。
見積もり内容が簡素すぎたり複雑すぎたりする業者は要注意です。業者の慣習なのか、取引相手との信頼関係を大事にしており見積もり内容を詳しく書かない業者も多いようです。
「解体工事 一式〜円」というように明細のない見積もり書や、素人にわかりにくい表現で埋まっているような見積もり書を受け取り不安を感じたらすぐに担当者に相談をしましよう。
いよいよ契約!契約書も気を抜かず5つのポイントを確認!
信頼できる業者が見つかり、契約内容に納得できたら請負契約を結びます。契約書で見るべき点は5つです。
①工事内容と範囲の特定
解体工事と言っても、全て取り壊すのか、一部を残すのか、一部のみ解体するのか、と詳しく特定されます。
事前に相談した内容と合致しているのかよく確認しましょう。相互のやり取りをより確実にする方法として、図面に作業範囲を明記したものを用意することも良いです。
②工事代金
まずは、見積もり時に提示された金額と相違が無いか、無断の書き換えが行われていないかを確認します。
さらに、工事代金の支払い時期が、解体工事から何日以内までなのか確認することも重要です。その際、一括払いなのか分割なのか、カード支払いが可能なのかも併せて見てみましょう。加えて、解体工事の支払いにローンや助成金を使用する場合は、その旨を事前に伝えておくとスムーズです。
③工期の目安
工期の目安が明記されていないと、工期が大幅に遅れているときに責任を問うことができなってしまいます。また、災害などやむを得ない事情で工期が遅れる際のどのように対処されるのか(例えば、遅延が判明したらすぐに施主に連絡をするなど)も決めておくと安心です。
反対に、人員や機材不足などの業者側の理由で遅れる場合、無断で追加費用を支払わなくて済むように事前に決めることもトラブルを避ける為に良いでしょう。
④瑕疵担保責任と損害賠償
法律用語だからと言って読み飛ばしてはいけません!
瑕疵担保責任は、もし解体後の状態に欠陥や不具合がみられ解体作業として不十分である(瑕疵がある)場合、業者側が負う責任の事です。瑕疵担保責任が明記されている事で、不具合があっても、一定期間に渡って業者側が責任を負い、施主は余計なコストの支払いを免れることができます。
また、損害賠償が発生するのは、作業中に一般人を怪我させてしまったり、他の建造物に傷をつけてしまった場合です。原則、業者側が責任を負いますが、より責任の所在を確実にする為に明記して負いた方が良いでしょう。
⑤引き渡しの時期
解体工事が終了時期は、必ずしも引き渡しの時期と同じではありません。一般的には、施主の立会いのもと作業の終了を確認してもらい、終了となります。
引き渡しの時期を明記することで、工事の遅れの判断基準にもなりますし、直接現場に立ち会えない場合のスムーズな引き渡しにつながります。
ご近所さんへの挨拶も忘れずに
解体工事中に騒音や埃等が発生する場合は特に、近隣住民の方にご迷惑をおかけするので事前に説明し、理解を得てもらいましょう。
業者の方が挨拶してくれることもありますが、施主も同行することでより良いコミュニケーションを取れるので、労力を惜しまずに挨拶に行き、円満なご近所づきあいを継続してください。
いよいよ解体作業!
工事の大まかな流れを以下のようになります。
外構の解体:重機の搬入や足場、養生の設置のためにスペースを確保します。
↓
足場、養生の設置:養生を設置することは、粉塵や木材の飛散防止、騒音の軽減に必要です。
↓
屋根、内装の解体:建設リサイクル法を遵守する為に、素材ごとに手作業で分別しながら解体していきます。
↓
建物本体の解体:壁や柱などの建物の主要部を解体するので、主に重機を使用します。粉塵の飛散を防止するために散水しながら行います。
↓
建物基礎、地中物の撤去:地中にある建物の基礎や配管などを解体、撤去します。ここで初めて明らかになる地中物もあるので、撤去のため追加費用が必要な場合もあります。
↓
整地:解体工事で掘り起こされた土地を平らにします。施主が立ち会って確認できます。
解体作業が終了してもまだ手続きが残っています!
解体工事が完了してもすべてが終わるわけではありません。
引き渡し
解体作業自体が終了したら、施主は現場に立会い最終確認をします。一般的に、ここで引き渡しとなり、正式に解体工事が終了します。
建物滅失登記申請
建物が取り壊されれば、登記簿にある家屋が無くなったことを登記するために、法務局に申請しなければなりません。
不動産登記法57条で、解体工事後1ヶ月以内に、その旨の滅失登記をすることが義務付けられているので必ず忘れずに行ってください。登記していなければ、その土地を売却することができなくなるばかりではなく、固定資産税として課税されてしまいますので、ご注意ください。
終わりに
解体工事の流れへの理解は深まりましたか?解体工事を依頼する時と、工事後の登記手続きが少々面倒ではありますが、全て必要なことなので都度確認しながら進めてみてください。
解体業者を選ぶことにストレスを感じるならば、少しお金はかかりますが中間業者に頼んで斡旋してもらう方法もあります。少しでもストレスとトラブルが少ない解体工事への手助けができていれば幸いです。
2020.11.27